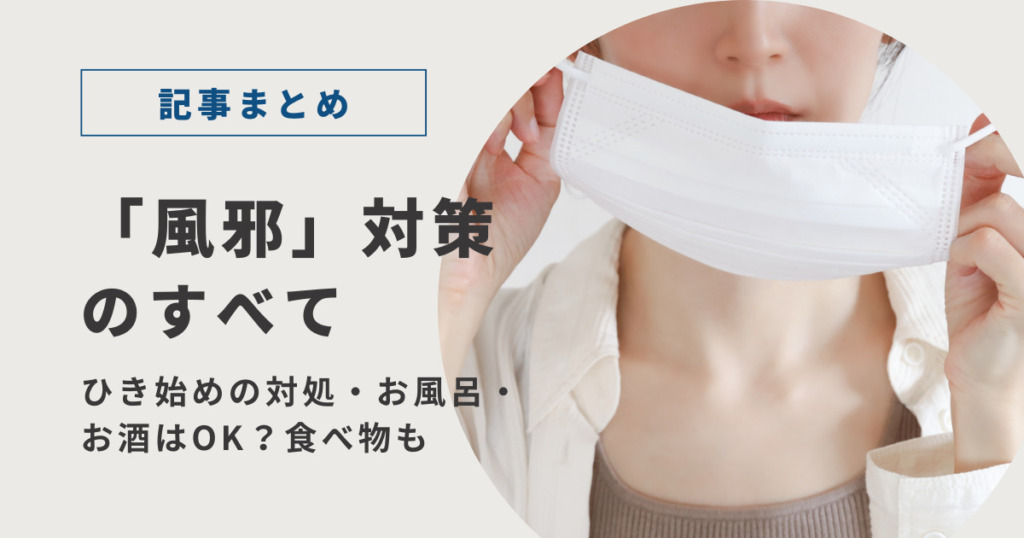風邪をひいたかも…と思ったら、すぐに対策をしましょう!
風邪の初期症状から、ひきはじめにおすすめの対処法や食事、病院の受診目安まで、医師が解説します。
熱が出そう…風邪のひき始めの対処法
風邪のひき始めには「体を温める」ことが大事!

風邪のひき始めで悪化させないためには、とにかく免疫力を高めることが大切です。
- 体を温める
- しっかりと栄養を補給する
- 睡眠時間を長めにとる
などの対処をとりましょう。
風邪をひきそうだな…というタイミングで市販薬に頼りたくなってしまいますが、実は風邪を悪化させないためにはなによりも免疫力を上げることが大事!
体温が上がることで免疫を活性化させ、ウイルスへの攻撃力を高めます。特に
を温めると冷えを予防することができます。
▼風邪のひき始めにいい市販薬や食事を知りたい方はこちらの記事をチェック!
風邪のひき始めにいい漢方薬や市販薬、悪化させないための食事などを詳しく解説しています。
合わせて読みたい

2020-01-08
「風邪ひいたかも…」
「ひきはじめで風邪を治してしまいたい!」
風邪の初期症状から、ひきはじめにおすすめの対処法や食事、病院の受診目安まで、医師が解説します。
風邪のひきはじめかも!「風邪の初期症状」
悪寒
肩こり
冷え
頭痛
喉に違和感がある
透明の鼻水が出る
といった症状が、風邪の初期症状といえます。
このような状態に気がついたら、すぐに対策を行えば、風邪は軽く済ませることが可能な場合もあります。
ひきはじめの風邪を「治す方法」は?
風邪をひいたときは、
体を温める
しっかりと栄養を補給する
睡眠時間を長めにとる
出歩くのを控える
といった対処を行ってください。
体を温める方法
首筋・手首・足首の「首」の付く3部分を温めましょう。
この部分が出ているとあっという間に体温が奪われ、冷えを招きます。
足首、手首、首回りが広く開いている服は避けてください。
長袖の服を着て、ネックカバーや靴下などを活用しましょう。
風邪のひきはじめの「過ごし方」
風邪のひきはじめは、睡眠をしっかりととり、体の免疫力を高めることが大切です。
このときに無理をしてしまうと、風邪が悪化しやすくなります。
体が弱っているため、出歩くのも避けましょう。
特に人込みは、細菌・ウイルスに感染しやすいので要注意です。
風邪のひきはじめの「食事」
風邪のひきはじめは、食事でしっかりと栄養を補給しましょう。
ただし、胃腸が弱っているときは無理せず、消化の良いものを食べてください。
栄養ドリンクを飲む
風邪のときは疲れもたまりやすいので、疲れをとる成分「アミノ酸」や「ビタミンC」が多いものを選ぶのがおすすめです。
風邪の初期症状に、手軽に栄養補給できる栄養ドリンクもよいでしょう。
寝る前に飲むのは避けて
栄養ドリンクの中には、カフェインが入っているものがあります。
カフェインは興奮作用があり、眠りにくくなる場合があるので、寝る前に飲むのは避けましょう。
カフェインの感受性は個人差がありますが、一般的には2時間前ほど、感受性の高い方は6時間以上あけるとよいでしょう。
また、栄養ドリンクからだけでは、体への栄養補給は不十分です。
食事をしっかり摂り、あくまでその補助という役目で取り入れましょう。
おすすめの食事
お鍋やスープ、グレープフルーツやみかん、緑黄色野菜などがおすすめです。
たんぱく質・鉄分・亜鉛・ビタミンC・ビタミンEを摂りましょう。
一つだけに偏るのではなく、満遍なく補給することが大切です。
これらの食事は免疫を高め、風邪を悪化させないよう体の働きを サポートしてくれます。
温かい鍋やスープは体を温め、一度に栄養のある食材を摂れます 。
エネルギー源になるじゃがいもや免疫力を高める緑黄色野菜のかぼちゃ・ブロッコリー・トマトなどを具材として入れるのがオススメです。
また、果物や生野菜からもビタミンを摂取しましょう。
グレープフルーツやみかんなどさっぱりしてビタミンCも多いのでおすすめです。
緑黄色野菜全般はビタミンCやβカロテンが多く、免疫力を高めます。
飲み物に関しては、水分摂取自体も大切ですが、ビタミンCが多い野菜や果物のジュースもオススメです。
ひきはじめの風邪に効く「市販薬」
ひきはじめの風邪は、市販薬を使うと悪化を防げることがあります。
出ている症状に合わせて、薬を選びましょう。
市販薬を飲む
風邪薬には様々な市販薬が販売されており、鼻水、喉の痛みなど、それぞれの症状に適した薬を選ぶとよいでしょう。
わからないときはドラッグストアなどにいる薬剤師に相談しましょう。
なお、風邪のウイルスに直接効くという風邪薬はないため、どの薬でも対症療法となります。
ご自身の症状に合わせた市販薬を早めにとると、辛い症状が楽になりよく眠れるようになり、風邪の悪化予防につながることがあります。
漢方薬を飲む
風邪対策の初期におすすめの漢方薬は「葛根湯」です。
葛根湯には発汗を促して体を温める作用があるため、服用すると抵抗力が高まります
風邪の初期で「寒気」があるときに服用すると良いでしょう。
さらに「ひどい寒気、発熱、体の節が痛む」などの症状があるときは麻黄湯がおすすめです。
漢方薬も「使用できないケース」「年齢制限」に注意
漢方薬であれば体に優しいと思われている方もいますが、使用できない方や年齢制限もありますので、使用前に説明や容量を確認してください。
風邪のひきはじめにNGな行動
40度以上の高熱がある
鼻水が出て止まらない
喉の痛みが強いが鼻水は出ていない
微熱が1週間以上続いている
といった症状には、風邪以外の病気が疑われます。
鼻水ばかり出て、喉の痛みや発熱がない場合は「アレルギー性鼻炎」、高熱が急に出た場合は「インフルエンザ」、鼻水がないのに喉が痛む場合は「扁桃周囲膿瘍」といった病気が疑われます。
いずれも重症化するリスクがあるため、放置しないようにしましょう。
また、微熱が何日も続く場合は、「A型肝炎」、「白血病」、「HIV」などの重い病気も考えられます。
症状に心当たりがあるときは、一度医療機関で相談してください。
<扁桃周囲膿瘍>
口の奥の方にある口蓋扁桃に細菌感染を起こして、炎症、膿などを持ってしまう病気です。
発熱する場合もあり、風邪と間違えやすいですが、鼻水は出ません。
口が開きにくい、物が食べられないなども症状も出ます。
こんなときは早めに受診を
症状が重い場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
風邪は特効薬がないので対症療法(※)がメインですが、なかなか治らないときは、医師の指示に従うことでより早い改善が期待できます。
※対症療法…起こっている症状に対して対処していく方法。熱がでていれば解熱剤、炎症が起きていれば炎症止めを使用する。
赤ちゃんや高齢者は要注意
小さな赤ちゃんや高齢者は、風邪が一気に症状が悪化しやすいので要注意です。
様子がいつもと違う場合は、早めに医療機関へ連れて行きましょう。
内科を探す
※記事中の「病院」は、クリニック、診療所などの総称として使用しています。
風邪に栄養ドリンクは効く?おすすめはコレ

栄養ドリンクは、様々な体にいい・栄養となる成分を複合的に配合して、一気に補給できるものです。
風邪のひき始めに飲めば、今後の体調不良に備える栄養をチャージできます。
▼栄養ドリンクの飲むタイミングやおすすめのドリンクの選び方はこちらの記事をチェック!
風邪の時に栄養ドリンクを飲むタイミングなどを詳しく解説しています。
合わせて読みたい

2019-12-03
風邪で体力を消耗したときに、頼りたいのが栄養ドリンク。
「風邪のひき始めに栄養ドリンクを飲むいいってホント?」
「栄養ドリンクはいつ飲めばいいの?」
おすすめの栄養ドリンクや、飲むタイミング、注意事項などを、医師が解説します。
栄養ドリンクは風邪に効くの?
栄養ドリンクは、様々な体にいい・栄養となる成分を複合的に配合して、一気に補給できるものです。
風邪のひき始めに飲めば、今後の体調不良に備える栄養をチャージできます。
また、風邪がよくなってきた時に飲めば風邪の時に摂れなかった栄養分の補給に役立ちます。
ただし、すべての栄養が網羅できるわけではありませんので、そこは注意してください。
風邪におすすめの栄養ドリンク
風邪の前後で栄養ドリンクを飲みたい時には、ノンカフェイン・ノンアルコールのものを選びましょう。
カフェインが配合されていると目が覚め、神経が高ぶり、質の良い睡眠・深い睡眠がとりにくくなります。
また、風邪で体が辛い時にアルコールの分解までさせると体に負担がかかります。少量でもアルコールが配合されている栄養ドリンクもあるので、確認するようにしましょう。
飲むタイミングは?
栄養ドリンクを風邪の時に飲むのであれば、ご飯を食べた時に一緒に摂りましょう。
風邪薬と一緒に飲むといいって本当?
風邪薬とアルコール入り栄養ドリンクを同時に摂ると薬の吸収が良くなったり、一部成分の働きが同調されてしまったりする恐れがあるのでやめましょう。
あくまで”食事のサポート”として飲むこと
おかゆやうどんといった食事も同時にとらないと栄養ドリンクの栄養も吸収が悪くなり、活かしきれません。
風邪の時の栄養補給を栄養ドリンクだけに頼ることはやめてください。それだけに頼ると栄養が偏り、足りない栄養もあります。また、風邪のときは胃腸が弱っているので栄養ドリンクが刺激になる場合もあります。
特に風邪が良くなってきて、食欲もあれば、食品からビタミンやミネラル、タンパク質などを摂り、より早く快方に向かわせましょう。
子どもに飲ませる場合は大人がしっかり管理を
多くの栄養ドリンクは、15歳以上を対象にされています。
また、飲みすぎは禁物です。
15歳以下の子ども用の栄養ドリンクもありますが、飲みやすいように糖分が高いので飲ませすぎは禁物です。子どもは、おいしいと思うと飲み過ぎたりするので、大人が管理するようにしてください。
風邪の時にお風呂は入っていい?悪化させない入り方

ひどい症状がなければ、入浴して構いません。
ですが、お風呂は体力を使うため、免疫力が低い状態で入ると風邪の悪化につながることもあります。冷えに注意して、長風呂せずにサッと短時間で入るのが望ましいでしょう。
特に、微熱の時や風邪のひき始めのうちはお風呂で体を温め、冷えないうちにゆっくり就寝すれば、風邪が悪化するのを防げる可能性があります。
ただし、高熱の時は体、力の消耗が激しかったりふらつきやめまいを起こす可能性があるため、入浴は避けましょう。
▼風邪の時のお風呂について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
お風呂で家族に風邪はうつる?子どもはお風呂に入らない方がいい?どれくらいの症状ならお風呂に入っていい?など詳しく解説しています。
合わせて読みたい

2019-12-13
風邪を引いたときに悩むのがお風呂です。
「入った方が良いの?入らない方が良いの?」
結局のところ、風邪を早く治すにはどうするのがベストなのでしょうか…?
この記事では、風邪をひいた時のお風呂について解説します。
風邪をひいたときお風呂に入っても良い?
重篤な症状がなければOK
重篤な症状がなければ入浴はしていただいて構いません。
全身症状を考慮して、入浴できるか判断してください。
風邪をひいているときは、発熱・鼻水・喉の痛み・咳・悪寒などの症状が総合的に現れます。
まず、高い熱が出ているときは脱水している可能性があります。湯船に浸かっての入浴は、さらに脱水を進める可能性があります。
また高熱の場合、急なふらつきやめまいによって、卒倒してしまう場合もありますので、無理に入浴するのは避けましょう。
風邪のひきはじめの入浴で悪化を防ぐ
風邪っぽい時にお風呂で体を温め、冷えないうちにゆっくり就寝すれば、風邪が悪化するのを防げる可能性があります。
入浴しても熱は下がらない!
実は、入浴して汗をかいても熱を下げることはできません。
汗は体温調節の役割があるため、入浴して汗をかくことで一時的に下がる可能性はあります。
しかし、炎症によって発熱している最中は、ウイルスと戦っているための発熱ですから、外から何をしても下げられないのです。(解熱剤は別です。)
まだふらつきやめまい、食欲もない時期は、無理な入浴はせずに水分補給をしてゆっくり安静にしてください。
お風呂は微熱に下がってから
微熱に下がって、体調が良くなってきていれば、汗を流す程度であれば問題ないでしょう。
しかし、病気の時は、判断能力が下がっています。急な体調不良を起こす場合もありますので、長湯は避けましょう。
お風呂の加湿された環境は喉・鼻の症状に良い
咳は、浴室の加湿されている環境では楽になります。鼻水も、入浴で体が温まると出やすくなります。
高熱はなく、喉や鼻の症状がつらいときは、お風呂に入ることで緩和されることもありますので、試してみるのも良いでしょう。
シャワーだけの場合は「冷え」に注意
熱が上がりきって汗をかいた後は、さっとシャワーを浴びて汗を流しても構いません。
浴室を出た後はすぐに着替えをして髪の毛を乾かし、冷えないようにしてください。
朝風呂は?
朝風呂は、前日の夜まで高熱があって、次の日もなんとなくフラフラするようであれば、お風呂で倒れるリスクもあるので控えた方が安心です。
特にフラフラせず、不快感をさっぱりさせるほどの軽い入浴であれば問題ありません。
朝は、体温が低いので体調が良く感じる場合もありますが、夕方にかかって人間の体温は上がっていきます。
朝だけで判断せずに、夕方や夜、熱が上がらないかで入浴が可能かを判断しましょう。
赤ちゃんが風邪をひいたときの入浴
赤ちゃんはまだ体力がないので、風邪にプラスして入浴をすると一気に体力を消耗してしまう場合があります。
体調が元どおりになるまでは、入浴は避けて汗を拭いてあげましょう。
風邪はお風呂でうつる?
お風呂で風邪がうつる可能性は低い
風邪のウイルスは、高温多湿では生存できません。
そのため、入浴場所で風邪をもらってしまう可能性は低くなります。
ノロウイルスなどウイルス性胃腸炎は注意!
お腹の風邪と別名もある「ウイルス性胃腸炎の原因菌(ノロウイルスやロタウイルス)」は、お風呂場でも死滅しません。
保菌者と一緒の入浴やその後の入浴で感染する場合もあります。
ウイルス性胃腸炎を発症している場合は、入浴は避けましょう。
次に誰も入らないお湯(一番最後のお風呂)に浸かる、シャワー浴の場合なら大丈夫です。そのあとは、しっかり浴槽周辺、イス、洗面器などをしっかり掃除し、次の人が入るようにしましょう。
お風呂の適温
お風呂のお湯は、通常時でも高すぎれば心臓や肌に負担になります。
また、ぬるすぎれば体が冷えますので、40〜41度くらいのお湯に入りましょう。
まとめ
お風呂に入ることで、咳や鼻水の症状は、良くなる場合があります。熱が微熱程度で、だるさや気分の悪さがなければ入浴してみましょう。
血流も良くなるので、体も軽く感じます。ただし、長湯は、のぼせや疲れの原因に。出てからの冷えにも注意して入浴してくださいね。
風邪の時にお酒は飲んでOK?

風邪をひいている時は、お酒を飲むのはやめましょう。
お酒を飲むと、血流がアップして頭痛がひどくなり、アルコールを分解するために肝臓が働かなくてはならず、逆に体は疲労が増し、風邪の症状も悪化させる可能性が高いと考えられます。
また、お酒には利尿作用があるため、水分が奪われて脱水になってしまうリスクがあります。
風邪で発熱している時は、ただでさえ水分が失われているのに、さらに利尿効果で水分が排出されると脱水症状がすすむ場合もあるのです。
▼お酒を飲んでしまったら?お酒は喉の菌にいい?詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!
風邪の時にお酒を飲むと睡眠の質が低下するのか、お酒を飲んだ後は風邪をひきやすくなるのかなどを詳しく解説しています。
合わせて読みたい

2019-12-05
風邪をひいているとき、お酒を飲んでもいいのでしょうか?
お酒に強い人の中には、風邪をひいたときでも普段通りお酒を飲むという人も多くいますね。
ですが、風邪のときは普段より酔いやすくなったり、薬と飲酒の飲み合わせは危険だと耳にします。
また一方では、風邪の症状を改善するために飲む「たまご酒」などもあります。
この記事では、風邪をひいたときのお酒はOKかNGか、医師に詳しく解説してもらいました。
風邪のときお酒はOK?
風邪のときにお酒を飲むのはNG
風邪は、発熱・悪寒・喉の痛み・咳・鼻水など多くの体の不調が現れます。
このような状態でお酒を飲めば、一時的に麻痺した感覚となり、楽になったと感じる人もいるかもしれません。
しかし実際は、血流がアップして頭痛がひどくなり、アルコールを分解するために肝臓が働かなくてはならず、逆に体は疲労が増し、風邪の症状も悪化させる可能性が高いと考えられます。
睡眠の質の低下、脱水症状のおそれも
飲酒は睡眠の低下を招き、体力の低下により風邪を長引かせる要因となる可能性もあります。
また、お酒には利尿作用があるため、水分が奪われて脱水になってしまうリスクがあります。
風邪で発熱している時は、ただでさえ水分が失われているのに、さらに利尿効果で水分が排出されると脱水症状が増悪する場合もあるのです。
お酒で喉のアルコール消毒!?
中には、喉が痛いとアルコール消毒と言って飲酒する方がいますが、一般的なお酒はアルコール濃度が低いため、殺菌などの働きは期待できません。
風邪のときは酔いやすい?
風邪のときは体の免疫力が落ちて体力も消耗しているため、お酒に酔いやすくなります。
風邪薬とお酒の飲み合わせには注意!
風邪薬を服用して飲酒すると危険!
風邪薬を飲んでアルコールを摂取すると、薬が通常より早く吸収され、成分が過剰に働くリスクが上がります。
風邪薬を飲んだ後にアルコールをとると、眠くなる成分が働きすぎて思わぬ事故につながった事例もあります。
風邪薬を飲んだらアルコールの摂取は控えてください。
飲んでしまったときの対処法
気が付いた時点でやめましょう。
水分補給を行い、安静にして睡眠をとることをおすすめします。できれば家族やパートナーと一緒に眠り、変化があった場合は対応してもらいましょう。
お酒を飲まなければいけないときは?
薬によって体から抜ける期間は異なるため、薬剤師や医師に確認しましょう。
通常病気や風邪のときは、アルコールは飲まないようにした方が体のためです。
内科を探す
お酒を飲んだあとは風邪を引きやすい
お酒を飲むとリラックスして楽しい気分になれるので体にいい気もしますが、実際には睡眠不足や肝臓機能の疲労などを招き、体の免疫は低下しています。
その隙にウイルスや細菌に感染してしまい、風邪や体調不良を発症するリスクが高まるのです。
たまご酒や甘酒で風邪対策?
たまご酒の効果は?
現在ではあまりおすすめできません。
たまご酒は昔、栄養のある食べ物が貴重だった頃に卵という栄養価値の高いものと温めた日本酒を混ぜ合わせ、栄養摂取とアルコールで体を温め、良く眠れるようにするという働きを期待したもののようです。
酒粕ではなく米麹の甘酒がおすすめ
酒粕が原料の甘酒はアルコールが入っているのでおすすめできません。
米麹が原料の甘酒は、アルコール分が入っていないので風邪対策に活用できます。
甘酒にはブドウ糖、オリゴ糖、必須アミノ酸、ビタミンB群など、風邪予防に働く栄養素が多く含まれています。
風邪をひいて食欲がないときの栄養補給にも良いですね。
まとめ
風邪のときのお酒は、いっときの体が温まる働き以外には、良い働きは期待できません。
風邪の症状の悪化や治癒を長引かせる原因になりかねません。
風邪のときは、アルコールは、控えて食事や睡眠をしっかりとり、早く体調を元に戻したいですね。
ビタミンCで風邪は治る?

ビタミンCは、風邪を直接治すわけではありませんが、免疫力や抵抗力を上げるのに役立つため、日々の風邪予防につながると考えられています。
ビタミンCは薬ではないため、風邪の症状が出た後に急にビタミンCを摂取してもあまり有効とは言えないとされています。
ただ、ビタミンCには免疫力や抵抗力を向上させる働きがあるため、体に風邪のウイルスが入ってしまった場合でも症状が出ずに治る可能性があります。
毎日こまめに摂取することで日々の風邪予防に役立つため、意識して摂るようにするのがおすすめです。
▼ビタミンCは大量に摂取していい?ビタミン注射は効く?この記事をチェック!
ビタミンCが豊富な食べ物や飲み物、ビタミン注射の効果、ビタミンは大量に摂取していいのかなどを詳しく解説しています。
合わせて読みたい

2020-03-16
「ビタミンCが風邪に効くって本当?」
「ビタミンCを大量に摂ったら早く治る?」
風邪にビタミンCがよいと言われる理由、効かないと言われる理由を、それぞれ医師が解説します。
ビタミンCの含有量が多い食べ物・飲み物、より効果的な摂り方もご紹介しています。
風邪にはビタミンCがいいって本当?
現在、ビタミンCの効能は重要視されていますが、ビタミンCが風邪の治療に有効であるかどうかは賛否両論あるようです。
風邪に「ビタミンCがよい」といわれている理由
コラーゲンを合成する
免疫力・抵抗力を向上させる
などが理由といわれています。
ビタミンCには、免疫力や抵抗力を向上させる働きがあります。
そのため、毎日こまめに摂取することで、日々の風邪予防につながると考えられています。
コラーゲンは、体を形成する全タンパク質のおよそ3割を占めており、細胞同士を繋ぐ結合組織・骨・血管・筋肉・各器官等を強化する働きを持っています。
ビタミンCがコラーゲンを合成することによって、毛細血管が強化され、血液の流れをスムーズにして十分な栄養を各器官に送り、正常な機能をサポートします。
また、ビタミンCは免疫細胞を活性化して白血球の機能を補助する働きがあります。
血中の白血球、リンパ球はビタミンCを豊富に含んでいます。
そして、体内に細菌等の異物が侵入した際に攻撃してくれます。
風邪に「ビタミンCが効かない」といわれている理由
即効性のあるものではない
風邪をひく確率自体は下がらない
などが理由といわれています。
風邪の症状が出現した後に、急にビタミンCを摂取しても、あまり有効とは言えないとされています。
ビタミンCは薬ではないので、即効性が期待できるものではありません。
そのため、日頃からビタミンCを含む食品等を意識して摂取することが大切と考えられています。
また、臨床試験の結果から、一般集団において、ビタミンCを1日0.2g摂取しても、風邪をひく確率は下がらなかったと確認されています。
現在、ビタミンCの効能は重要視されていますが、ビタミンCが風邪の治療に有効であるかどうかは賛否両論あるようです。
ビタミンCは大量に摂取したほうがいいの?
ビタミンCは水溶性のため、多めに摂取しても尿から体外へと排泄されます。
そのため、摂り過ぎを心配する必要はほぼないと考えられています。
しかし稀に、ビタミンCの大量摂取により、吐き気・下痢・胃痙攣等が起こる場合がありますので、気を付けましょう。
1日の摂取目安は?
15歳以上のビタミンC摂取推奨量は、100mg/日とされています。
栄養ドリンクやサプリメントは風邪にいいの?
日常的にビタミンCの栄養ドリンクやサプリメントを摂取している場合、風邪症状が出る期間が短縮されたり、症状が軽く済んだりするケースもあるようです。
しかし、風邪をひいた後にサプリメントを摂取しても効能はあまりないと考えられています。
液剤でも錠剤でも、同じ成分で同量含有されていれば効能は同じと考えられています。
ビタミンCは排泄されやすいため、1度に摂るのではなく、朝、昼、晩というように分けて摂るようにしましょう。
他の薬を服用している場合は注意!
ビタミンCサプリメントは、他に服用している薬がある場合には注意が必要です。
サプリメントは食品と違い、栄養素が凝縮して入っているので、相互作用を起こす恐れがあります。
例えば、腎臓疾患がある場合や、利尿剤を飲んでいる方がビタミンCサプリをとると、尿中のシュウ酸がカルシウムと結束し、尿路結石や腎臓結石を引き起こす可能性があるので注意が必要です。
ビタミンCが豊富な食べ物・飲み物
アセロラ 1700mg
ブロッコリー 120mg
いちご 62mg
キウイフルーツ 69mg
緑黄色野菜(小松菜39mg、キャベツ41mg)
トマト 15mg
じゃがいも 35 mg
グレープフルーツ 36mg
緑茶(玉露 抽出液 19 mg)
赤ピーマン 170 mg、緑ピーマン 76 mg
ゆず 160 mg
レモン 100 mg
(数値は100gあたりのビタミンC含有量)
などの食品にビタミンCが豊富に含まれています。
その他、みかん・オレンジジュースもおすすめです。
トマトジュースにレモン(レモン汁)を加えると、ビタミンCの相乗作用が期待できます。
緑黄色野菜もおすすめ
特に、緑黄色野菜は比較的ビタミンCも多く、その他の栄養素もバランスよく含まれているので、風邪のときには効率的に栄養素を摂取できます。
おすすめ常備レシピ「ゆずジャム」
<材料>
ゆず:1個(約50g)
砂糖:25g(ゆずの重量に対して50%分の砂糖を使用する。きび砂糖等でも可)
(作り方)
ゆずを半分に切って種を除去する
ゆずを薄切りにしてから細かく刻む
砂糖を投入し混ぜる
砂糖が溶けてとろっとした状態になったら完成
「ビタミン注射」って何?
ビタミン注射とは、注射や点滴によって、体内にダイレクトにビタミンCを注入する方法です。
通常の食品やサプリメントからの摂取に比べて、有効な成分を高濃度で体内に取り入れることが可能になり、全身細胞にビタミンCを高濃度で届けられます。
そのため、風邪等の疾病予防にも有効と考えられています。
また、高濃度ビタミンC点滴やビタミン注射は基本的に保険適用外です。
費用は各医療機関により異なりますが、10000円~15000円/1回、25gが目安と考えられます。
風邪をひいた後に注射すると早く治る?
ビタミン注射によって風邪が早く治るということは考えにくいです。
しかし、風邪をひくと体内のビタミンCが消耗するので、その補充としては役立ちます。
副作用はある?
ほぼ副作用なく受けられる療法とされていますが、稀に以下のようなケースがあります。
腎不全・心不全・透析治療中・胸水・腹水・不整脈等の持病がある場合、点滴を用いて血管内に水分を注入することで症状の悪化を招く恐れがあるため要相談です。
点滴をはじめる際、刺入部に痛みが生じる場合があります。
稀に低血糖になり、めまい、冷や汗等の症状が出る場合があります。
高濃度ビタミンC点滴は利尿作用があるので口渇になる場合があります。
ビタミンCはカルシウムを尿として排泄する働きがあるため、稀に低カルシウム血症を起こす場合があります。
ごく稀に結石が発生する場合があるようです。
ごく稀に薬剤に対するアレルギーによって、かゆみ、蕁麻疹、息苦しい等の症状が出る場合があるようです。
また、高濃度ビタミンC点滴療法を受けるには、はじめにG6PD採血※を行い、赤血球膜の遺伝子酵素異常※の有無を確認する必要があります。
※G6PD採血
赤血球機能を維持するうえで重要なグルコース-6-リン酸脱水素酵素があるかを確認する採血です。欠損していると、ビタミンC点滴によって、貧血などを起こす恐れがあります。
※赤血球膜の遺伝子酵素異常
グルコース-6-リン酸脱水素酵素が少ない、または欠損している状態を指します。
何科で受けられる?
美容皮膚科、内科、整形外科等、幅広い分野で取り扱いがあります。
▼参考URL
医療法人 清友会 笠松病院 ビタミンCについて
医療法人 愛恵会 湘南メディカル記念病院 風邪を早く治すために覚えておきたい 3つのポイント
一般社団法人 愛知県薬剤師会 ビタミン
大塚製薬 ビタミン総合
厚生労働省「統合医療」に係る情報発信等推進事業「統合医療」情報発信サイトビタミンC
福岡天神内視鏡クリニック 高濃度ビタミンC点滴療法
38度の熱がある時。消費カロリーは?ダイエットになる!?


消費カロリーは、体温が1度上がるごとに約12~13%増加するとされています。
そのため一般成人の平均的な基礎代謝量と体温で考えると、おおよそ下記の消費カロリーになると考えられます。
- 女性→約336キロカロリー
- 男性→約420キロカロリー
発熱で消費カロリーが増えるのは、体温が上昇する際、多くのエネルギーを必要とするためです。
300~400キロカロリーというと、コンビニのメロンパン一個分くらいのエネルギー量なので、けっこうな消費カロリーになることがわかりますね。
▼咳もカロリーを消費する?発熱で痩せるのはなぜ?この記事をチェック!
咳やくしゃみの消費カロリーや、発熱によって痩せることはあるのかなどを詳しく解説しています。
合わせて読みたい

2023-12-15
「38度の熱で寝込んでいたら、痩せた!」
「発熱でずっと寝ていただけなのに、痩せるのはなぜ?」
その理由の一つは、熱によって消費カロリーが増加することです。
この記事では、38度の熱が出ると消費カロリーはどれくらい増えるのか、解説します。
風邪で体重が減った状態をキープしたい方も、ぜひチェックしてみてください。
38度の熱の消費カロリーは?
消費カロリーは、体温が1度上がるごとに約12~13%増加するとされています。
そのため一般成人の平均的な基礎代謝量と体温で考えると、おおよそ下記の消費カロリーになると考えられます。
女性→約336キロカロリー
男性→約420キロカロリー
※平熱が36度の場合です。
発熱で消費カロリーが増えるのは、体温が上昇する際、多くのエネルギーを必要とするためです。
300~400キロカロリーというと、コンビニのメロンパン一個分くらいのエネルギー量なので、けっこうな消費カロリーになることがわかりますね。
なぜ?発熱で痩せる3つの理由
発熱や咳などで消費カロリーが増加する
食欲が低下する
汗をかいて体の水分量が減る
発熱で痩せる理由として、上記3つが考えられます。
発熱や咳による消費カロリーの増加
前述のとおり、発熱すると消費カロリーが増加します。風邪で咳やくしゃみなどの症状がある場合は、もっと消費カロリーが増えると言われています。
咳を一回するだけで2キロカロリー、くしゃみは4キロカロリーも消費するのだそう。
一日中咳やくしゃみが止まらないような状態では、かなりのエネルギーを消費することになるでしょう。
食欲の低下
発熱によって食欲が低下して、いつも通り食事が摂れなくなる人も多いですよね。十分な食事が摂れていないと、消費カロリーが摂取カロリーを上回るため、痩せてしまいます。
体の水分量の減少
熱が出るとたくさん汗をかきます。発汗によって体の水分が抜けると、当然その分の体重が減ります。
顔もげっそりして、痩せた印象になるでしょう。
ということは…風邪はダイエットのチャンスってこと?
「消費カロリーが増えて食欲が減るなら、痩せるチャンスかも!」
そんな風に思う方も多いのではないでしょうか?
残念ながら、風邪や発熱で体重が減少するのは一時的で、すぐに元の体重に戻ってしまうケースがほとんどです。
体が本調子になれば、基礎代謝は正常になり、食欲も回復します。汗をかくことで低下した体の水分量も元に戻ります。
また、風邪や発熱によって体重が減少するのは、筋肉と水分量が減るからです。脂肪はほとんど減っていないと考えられます。
筋肉量が減って余分なお肉は残っている状態なので、理想的な痩せ方とは言えません。
減った体重をキープする方法はある?
「理想的な痩せ方ではない」とはいえ、せっかくなら減った体重をキープしたいですよね。
体調が回復した後のリバウンドを避けるためには、
食事の見直し
運動習慣を取り入れる
良質な睡眠をとる
ダイエットの基本である上記3つを実践しましょう!
食事はタンパク質を中心にバランスよく
肉や卵、大豆製品、乳製品などを積極的に食べて、タンパク質を摂取しましょう。
タンパク質は筋肉の材料となるため、代謝の向上に繋がります。
一日に摂取するタンパク質の推奨量は、男性なら65g、女性なら50gとされているので、こちらを目安にするといいでしょう。
食物繊維やビタミンが豊富な野菜類、海藻類も意識して摂るようにしてください。
特定のものばかり食べるのではなく、色々な食材からバランスよく栄養を摂ることが大切です。
筋トレ×有酸素運動で太りにくい体に
運動は、筋トレと有酸素運動を組み合わせて行うと、太りにくく痩せやすい体作りに役立ちます。
筋トレは「スクワット」がおすすめ
筋肉量が増えると、基礎代謝が上がって脂肪が燃料しやすくなります。
スクワットで下半身の大きな筋肉を鍛えて、効率よく筋肉を増やしましょう。
一日に10回×2~3セットを、週3回くらいのペースで続けてみてください。
有酸素運動は無理なく継続できるものを
有酸素運動は、今ある脂肪を燃やすのに役立ちます。
ウォーキングやヨガなど取り入れやすい有酸素運動を、一回に30分以上、週2日程度実践しましょう。
あまりハードな運動をして続かないと意味がないので、継続できる強度で実践することを心がけてください。
以上のように、風邪で減った体重をキープする方法は、健康的な生活習慣を維持することに他なりません。風邪が治ってもリバウンドしないように、自分の体と向き合ってください。
無理は禁物!運動は体調が回復してから
体調が万全でない状態で運動するのはNGです。無理をすると、発熱などの症状がぶり返すおそれがあります。まずはしっかり休んで、体調が良くなってからトレーニングを開始しましょう。
良質な睡眠で「痩せホルモン」を分泌させよう
発熱や風邪で減った体重をキープするためには、睡眠の質にもこだわりましょう。
質の良い睡眠は、成長ホルモンの分泌を促進します。成長ホルモンは、別名「痩せホルモン」とも呼ばれていて、筋肉の成長や脂肪の燃焼をサポートしてくれるダイエットの味方です。
反対に、質の悪い睡眠は、成長ホルモンの分泌を減らして、食欲を増進するホルモンを多く分泌するため、太りやすい状態になってしまいます。
睡眠の質を高めるためには、寝る前にリラックスできる環境を整えるようにしましょう。部屋は暗くして、寝具やパジャマは快適なものを選んでください。
また、睡眠時間は毎日6~8時間程度が理想とされています。寝不足は太りやすいだけでなく、病み上がりの体に悪影響となるので、しっかりと睡眠時間を確保しましょう。
参考
【タンパク質の必要量】タンパク質はどれくらい摂ればいい?|森永製菓株式会社
熱がある時にスマホをいじるのはNG?

熱がある時は、体の中の免疫がウイルスと戦っている最中。そのため、なるべく安静にして体を休めるほうが早く回復に繋がります。
スマホをいじることは休息の妨げになるため、できるだけ避けるのがおすすめ。ゆっくり目をつぶって休むのが望ましいでしょう。
スマホをいじっていると、脳や体を興奮させる働きを持つ交感神経が優位になるため、リラックスしにくくなります。
すると十分な休息が取れず、体調の回復が遅れる可能性があります。
横になっても眠れず、ついスマホを触ってしまう方も多いと思いますが、発熱時のスマホの使用は控えた方がいいでしょう。
▼室温は何度にするべき?熱がある時に避けることは?この記事をチェック!
熱がある時は室温や湿度は何度にするのが理想?解熱剤はいつ飲むべき?などを詳しく解説しています。
合わせて読みたい

2023-12-28
「熱がある時、スマホをいじるのはよくないの?」
「微熱ならゲームをしても大丈夫?」
熱がある時にやってはいけないことや、どのような過ごし方が適切なのかを解説。
早く熱を下げたい!という方は、ぜひ参考にしてください。
熱がある時にスマホをいじるのはNG?
どの程度の熱が出ているかにもよりますが、熱がある時にスマホをいじることは、あまりおすすめしません。
熱がある時は、ゆっくりと体を休めるべきです。
スマホをいじっていると、脳や体を興奮させる働きを持つ交感神経が優位になるため、リラックスしにくくなります。
すると十分な休息が取れず、体調の回復が遅れる可能性があります。
横になっても眠れず、ついスマホを触ってしまう方も多いと思いますが、発熱時のスマホの使用は控えた方がいいでしょう。
熱がある時「やってはいけないこと」
ゲーム
飲酒
脂っこい食事
運動
やってはいけないこと❶ ゲーム
ゲームをすると、スマホをいじるのと同様に交感神経を優位にして、体の休息を妨げます。
熱がある時はゲームを我慢して、しっかり体を休ませるようにしましょう。
やってはいけないこと❷ 飲酒
お酒は免疫力を低下させると考えられています。
さらに、風邪薬の効果を弱めたり、副作用を起こしたりする可能性があります。少なくとも、風邪薬を飲んでいる間は禁酒を徹底しましょう。
やってはいけないこと❸ 脂っこい食事をとる
発熱時は、胃の消化機能も低下しているので、脂肪分の多い食事は控えた方がいいです。
うどんやおかゆなど、消化の良いものを食べるようにしましょう。
やってはいけないこと❹ 運動
熱がある時の運動は、体力を消耗して症状の悪化につながります。発熱時は、極力安静にして過ごしましょう。
熱が引いてからも、数日間は激しい運動を控えてください。
熱がある時、お風呂やシャワーはどうする?
37.5度以下の微熱であれば、短時間でさっとお風呂に入ったり、シャワーを浴びたりしても構いません。
ただし、長湯は体力を消耗するのでやめましょう。
また、寒気やだるさがある場合も、お風呂やシャワーは控えてください。
市販の解熱剤は飲んでもいい?
熱のせいで食事や水分補給ができない
寝苦しくて睡眠がとれない
というように、熱に伴うつらい症状がある場合は、解熱剤を飲んでもいいでしょう。
解熱剤で一時的に体温を下げることで体が楽になります。
ただし、微熱の場合や、まだ熱が上がりきっていない段階での解熱剤の使用はおすすめしません。
微熱の状態で解熱剤を使用すると、熱が下がりすぎてしまう可能性があるからです。
また、悪寒などの症状があり、これから熱が上がりそうな状態で解熱剤を使用すると、免疫細胞の働きを妨げるリスクがあります。
熱が上がりきったサインは?
熱が上がりきると、悪寒がなくなり、汗がたくさん出るようになります。この段階であれば、解熱剤の使用で免疫細胞の働きを邪魔することはありません。
※解熱剤を使用する場合は、各製品の添付文書を必ず読むようにしましょう。妊婦や妊娠の可能性がある方、高齢者の方、治療中の病気や持病がある方は、解熱剤を使用する前に、お医者さんや薬剤師、登録販売者に相談してください。製品によっては、15歳未満のお子さんには使用できないことがあるので、注意してください。
早く治すための正しい過ごし方
寒気がある場合は体をしっかり温める
汗が出てきたら体を冷やす
水分を多くとる
部屋はエアコンで適温に保つ
❶ 寒気がある場合は体をしっかり温める
熱が上がってきている段階で寒気を感じるときは、衣類や布団を重ねて体を温めましょう。
体をしっかり温めることで、体の免疫細胞がウイルスや細菌と戦うのをサポートします。
❷ 汗が出てきたら体を冷やす
汗が出て寒気を感じなくなったら、効率よく熱を放出するために、少し薄着にしてください。
首や脇の下など太い血管が通る部分を、タオルを巻いた保冷剤などで冷やすのも効果的です。
また、汗はこまめに拭いて、濡れた衣類は取り換えるようにしましょう。
❸ 水分を多くとる
熱がある時は、脱水症状を防ぐためにしっかり水分補給をしてください。
水分補給の際は、汗と一緒に失われるミネラルを補えるように、経口補水液やスポーツドリンクを飲むといいでしょう。
❹ 部屋はエアコンで適温に保つ
寝苦しくならないように、エアコンで快適な室温をキープしましょう。
一般的に、室温は20~25度程度が理想とされています。
また、冬場は部屋の空気が乾燥しやすいので、加湿器を利用するのもおすすめです。湿度は、50%~60%程度にするといいでしょう。
熱が下がっても無理は禁物!
熱が下がった後は体力が落ちているので、数日間は安静にして過ごすようにしましょう。
ここで無理をしてしまうと、症状がぶり返す可能性があります。
解熱後2~3日はゆっくり過ごすようにして、体力の回復に努めましょう。
風邪薬と一緒にお酒を飲んでしまった!大丈夫?
副作用が強まる可能性があるので注意

風邪薬と一緒にお酒を飲んでしまった場合、薬の副作用が強まったり、体調に異常をきたしたりする可能性があります。異変を感じたらすぐに医師に相談しましょう。
風邪薬と一緒にお酒を飲むと、たくさんのリスクが生じます。控えるようにしましょう。
もし飲んでしまった場合、以下のような症状が出る可能性があります。
- 眠気やふらつき
- 血圧や心拍数の変化
- 胃痛や吐き気、消化不良
風邪薬の中には眠気を引き起こす成分が含まれているものがあり、アルコールを摂取することで眠気やめまいが増してふらつきに繋がることがあります。
またアルコールの消化管への悪影響によって消化不良や胃痛などの症状を引き起こしたり、風邪薬の成分とアルコールの成分が合わさり血圧や心拍数を変化させることもあるので注意が必要です。
何か体調に異変がある場合は、すぐに医師に相談するようにしましょう。
▼もし薬とお酒を一緒に飲んでしまったら…こう対処して!この記事をチェック!
風邪薬と一緒にお酒を飲んでしまったらどうする?薬を飲んでから何時間後ならお酒を飲んでOK?などを詳しく解説しています。
合わせて読みたい

2024-08-28
風邪薬と一緒にお酒を飲んでしまった時、健康リスクを抑えるにはどうすればいいのでしょうか。
なぜ風邪薬とお酒を一緒に摂取してはいけないのかの理由や、具体的な対処法、何時間あければ飲んでいいのかなどを医師が詳しく解説しています。
風邪薬と一緒にお酒を飲んでしまった…大丈夫?
副作用が強まる可能性がある。異常を感じたらすぐに医師に相談しよう
風邪薬と一緒にお酒を飲んでしまった場合、薬の副作用が強まったり、体調に異常をきたしたりする可能性があります。異変を感じたらすぐに医師に相談しましょう。
風邪薬と一緒にお酒を飲むと、たくさんのリスクが生じます。控えるようにしましょう。
もし飲んでしまった場合、以下のような症状が出る可能性があります。
眠気やふらつき
血圧や心拍数の変化
胃痛や吐き気、消化不良
風邪薬の中には眠気を引き起こす成分が含まれているものがあり、アルコールを摂取することで眠気やめまいが増してふらつきに繋がることがあります。
またアルコールの消化管への悪影響によって消化不良や胃痛などの症状を引き起こしたり、風邪薬の成分とアルコールの成分が合わさり血圧や心拍数を変化させることもあるので注意が必要です。
何か体調に異変がある場合は、すぐに医師に相談するようにしましょう。
薬の効果が変わってしまう可能性もある。効かなくなることもあるので注意
アルコールが風邪薬の吸収や代謝に影響を与えてしまい、薬の効果が変わることもあります。風邪の症状に効かなくなってしまうことも考えられるので、お酒と風邪薬を一緒に飲むのは避けましょう。
アルコールが胃や腸の粘膜を刺激してしまうことで薬の吸収を妨げてしまったり、肝臓に影響することで薬が通常よりも早く分解されたりしてしまうことがあります。
さらに、風邪薬の中に入っている解熱鎮痛剤や抗ヒスタミン剤などはアルコールと一緒に摂取すると作用が弱まることも考えられます。
なぜ?風邪薬とお酒を一緒に飲んではいけない理由
風邪薬とお酒を一緒に飲むと起こるリスク4つ
風邪薬とお酒を一緒に飲むと、風邪薬に含まれる成分とアルコールが相互作用を起こしたり、副作用を強めたり体に悪影響を及ぼす可能性があります。
副作用が強くなることで起こる主なリスクは
眠気やめまいの増加
肝機能への負担増加
消化不良や胃痛
血圧の低下や不整脈
の4つです。
1.眠気やめまいの増加
風邪薬に含まれる抗ヒスタミン剤は眠気を引き起こすことがありますが、アルコールも眠気を増す作用があるため、2つが重なることで過度の眠気やふらつきを感じることがあります。
眠気やめまいが増加すると注意力や反応速度が大幅に低下するので、生活に支障をきたすことがあります。
2.肝機能への負担増加
風邪薬の成分は肝臓で代謝されますが、アルコールも肝臓で処理されるため、アルコールと風邪薬を同時に摂取すると肝臓に対する負担が大きくなってしまいます。
その結果、肝機能に影響を及ぼしたり肝臓の疾患リスクを高めたりする可能性があります。
3.消化不良や胃痛
風邪薬が消化管の保護機能を妨げることがあり、その状態でアルコールが胃や腸に刺激を与えると消化不良や胃痛、吐き気を引き起こす可能性があります。
さらに風邪薬には胃酸の影響を受けやすい成分が含まれていることがあり、それにより胃酸が増加してしまい、胃痛へと繋がることもあります。
4.血圧の低下や不整脈
一部の風邪薬は血圧や心拍数に影響を与えることがあります。アルコールも同様に血圧や心拍数を変化させることがあるため、2つが合わさると血圧の低下や不整脈が起こる可能性があります。
風邪薬に入っていることが多い抗ヒスタミン剤や鎮静剤は欠陥を拡張し、血圧を低下させることがあります。アルコールも同じ作用があるため、2つを一緒に摂取するとその副作用が増幅してしまい、血圧が急激に低下する恐れがあります。
【対処法】風邪薬と一緒にお酒を飲んでしまったらどうする?
水を積極的に飲んで。アルコールの排出を早めよう
水を積極的に飲むことで、アルコールが体内で代謝される過程をサポートし、アルコールの排出を早めることができます。アルコールを早く体内から排出することで、風邪薬とアルコールが合わさることによる悪影響を軽減できます。
水をたくさん飲むことで、脱水症状の予防にもなります。
風邪薬を服用しているときは体がすでにウイルスと戦っているため、十分な水分が必要です。アルコールは利尿作用があるため体内から水分を多く排出してしまうので、水を飲むことで体内の水分バランスを保てます。
できるだけ安静にしていて。動かず休息をとろう
激しい運動をすると血液の循環が速まり、薬やアルコールが体内でより早く広がってしまうため、できるだけ安静にしているようにしましょう。動いていると血圧が急激に低下したり心拍数が上昇したりする可能性があります。
めまいやふらつきがある場合は動き回るとケガをする恐れもあるので、なるべくベッドなどに横になり、アルコールが抜けるまで安静にしているのが望ましいです。
めまいやふらつき、胸の違和感がないかよく体調を観察して
もしもめまいやふらつき、胸の違和感などが強い場合には早めに医師に相談するのが望ましいです。よく自分の体調を観察して、心拍数の上昇がないか、息苦しさがないかなどをよく観察することが大切です。
何時間後ならお酒を飲んで大丈夫?風邪薬の正しい飲み方
薬を飲んでからお酒を飲むなら4~6時間はあけよう
一般的には、お酒は風邪薬を飲んでから最低でも4~6時間ほどあけてから飲むのがいいとされています。ですが、時間は関係なくできるだけ風邪薬を飲んでいる期間はアルコールを避け、風邪が治ってから飲むようにするのが望ましいです。
風邪薬の成分が体内で代謝され、その後排出されるまでは4~6時間かかると言われています。
薬の成分がある程度体外に排出された後であれば最低限副作用のリスクを減少することができますが、リスクがゼロになるわけではありません。
なるべく風邪薬を飲んでいる期間はアルコールの摂取を避けるようにしてください。
注意!薬を飲んでから1~2時間はお酒を飲まないで
特に、風邪薬を飲んでから1~2時間は薬の成分の血中濃度がピークに達するため、お酒を飲むのは絶対に控えてください。
薬の効果が強く残っている間にアルコールを摂取すると、副作用が強くでる可能性があります。健康被害が起こるリスクも高くなるのでやめるのが望ましいです。
お酒を飲んでから薬を飲む場合は6~12時間程度あけよう
お酒を飲んだ後に風邪薬を飲む場合は、6~12時間程度あけることが望ましいです。一般的にアルコールが肝臓で代謝され、血中アルコール濃度が下がるのが6~12時間程度のため、それくらいの時間をおけば副作用による悪影響を避けられると考えられます。
薬とアルコールの相互作用による副作用を避けるためには、体内のアルコール濃度が低下し、薬の服用時にアルコールがほとんど残っていない状態にする必要があります。
一般的には6~12時間でアルコールが代謝されると言われているので、お酒を飲んでしまったら風邪薬を飲むのは半日程度あけてからにするといいでしょう。
もちろん個人差も大きく、風邪の症状などにもよるので一概には言えないため、医師に相談するのがおすすめです。
服用回数が少なくていい風邪薬を使うのもひとつの手
1日3回服用する必要がある風邪薬より、1日2回服用の風邪薬の方が薬を飲む間隔が長くなるため、お酒と風邪薬の摂取時間をあけやすくなります。もちろんお酒を飲まないにこしたことはありませんが、自分のライフスタイルに合わせて風邪薬を選ぶこともできることを知っておくのもいいでしょう。
ただし、服用回数や時間間隔に関わらず、体内に風邪薬の成分が実際どれぐらい残っているかによってアルコールとの相互作用による副作用の強さは変わります。
体調に異常が出る可能性もあるので、できれば医師と相談しながら服用するようにしてください。
1日2回服用の風邪薬
持続性パブロン錠
>楽天市場で探す
>Amazonで探す
新コンタックかぜEX持続性
>楽天市場で探す
>Amazonで探す
この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。
【食べ物】風邪を早く治したいときに。これを食べよう

風邪の予防や、風邪をひいた時は
などを食べるといいでしょう。
▼ひとつひとつの食べ物の風邪への効果を知りたい方はこの記事をチェック!
合わせて読みたい

2019-04-24
風邪の流行時期には、マスクや手洗いなどで予防をする方が多くいます。もちろん、風邪を予防するためには、十分な睡眠とバランスの良い食事が基本です。
食べたものが未来の体を作ります。日々の食事管理からも風邪予防はしっかりおこなっていきましょう。
今回は特に風邪予防に働きかける食べ物をご紹介いたします。
風邪予防に良い食べ物
にんにく
風邪の予防には、免疫力を高めること、ウイルスや細菌に打ち勝つ体づくりがポイントなんです。にんにくに含まれているにおい成分のアリシンには、免疫力を高める働きがあり風邪予防には有効な食材のひとつですよ。
にんにくの成分は風邪のウイルスから体を守るので、風邪が流行する寒い季節は取り入れていくと予防になります。
また、にんにくは食欲も増進する働きがあるので、疲れ、ストレスなどで食欲が落ちているときに取り入れるといいですね。
生のにんにくは胃腸への刺激が強いので、加熱して食べると刺激が和らぎ、お勧めです。風邪の症状がひどい場合に無理して食べると刺激が強すぎることもあるので、風邪の予防としてうまく取り入れるようにしましょう。
りんご
風邪をひいたときにりんごを食べる人は多いのではないでしょうか。りんごには風邪をひいたときに必要な栄養素が豊富に含まれているので、風邪をひいたときには積極的に取りたい食材です。
風邪のときは、発熱や食欲減退によって、脱水になりやすい状態です。りんごは水分も豊富で、甘味もあるので食べやすいため、風邪のときにはお勧めです。消化する力も弱っているので、すりおろして食べると胃腸にも負担をかけず食べられます。
また、りんごには整腸作用がある水溶性の食物繊維も豊富に含まれているので風邪でお腹の調子がすぐれないときでも食べられます。すりおろすのが大変な場合は、ミキサーなどにかけてジュースにするのも良いですね。
にんじん
風邪のときに特に必要とされるビタミンとして、ビタミンA(β-カロテン)、ビタミンE、ビタミンCがあげられます。ビタミンCは上記のリンゴでも摂取することができます。これらのビタミンは抗酸化作用や免疫力を高める働きがあるため、風邪で弱っている粘膜を保護するために役立ちます。そして、この栄養分が豊富な食材のひとつがにんじんです。りんごと同じようにすりおろしてジュースやポタージュなどにすれば、食べやすく消化もしやすくなります。
ヨーグルト
ヨーグルトは風邪予防にも役立ちます。
ヨーグルトに含まれている乳酸菌が腸内環境を整えてくれるためです。腸内は体内の免疫細胞を作る働きがあるため、腸内環境を整えると免疫力を高めることにつながります。
また、ヨーグルトは喉越しがよくひんやりと食べやすい食材でもあるので、風邪をひいたときの栄養補給としてもおすすめです。
乳酸菌だけでなくたんぱく質も含んでいるので、風邪で食欲がなかったり、喉に痛みがあったりするときなどに取り入れてみましょう。
風邪をひいたときや風邪予防には十分な睡眠と栄養源となる食事が基本です。今回ご紹介した食材を取り入れて風邪に負けない体を作りが大切です。風邪をひいてどうしても食欲がないときは、食べられるものを、少量でも口にして栄養源とするといいですね。
【参考文献】
朝日新聞社出版「栄養素図鑑と食べ方テク」中村丁次 監修
風邪の潜伏期間は?何日後までうつる?

風邪のウイルスに感染すると、平均2~5日の潜伏期間を経て、熱や鼻水などの症状があらわれます。
個人差はあるものの、ウイルスに感染してから発症するまで1〜3日程度のものが多いです。
新型コロナウイルスのように発症まで1日〜14日と幅があるものもあります。
風邪のウイルスの「感染期間」はいつまで?

風邪ウイルスの感染期間は、潜伏期間と症状がなくなるまでの期間を合わせた期間で、多くは1週間程度でしょう。
風邪の感染力が最も強いのは発症して1〜2日です。
ウイルスは、くしゃみや咳などで飛び散ります。
症状が弱くなっても咳やくしゃみ、接触などがあれば、2~3日間は他人にウイルスをうつしてしまう可能性があります。
また、寝不足や体力が落ちているのときは、症状が長引きやすくなり、感染力も維持されやすいです。
▼風邪が人にうつる期間、うつる確率など知りたい方はこの記事をチェック!
潜伏期間は人にうつる?どれぐらいの確率で人に風邪はうつる?などを詳しく解説しています。
合わせて読みたい

2020-01-09
風邪ウイルスの潜伏期間について、お医者さんに詳しく聞きました。
「風邪ウイルスは潜伏期間中もうつるの?」
「発症前に治す方法はあるの?」
といった疑問にもお答えします。
風邪ウイルスの潜伏期間はどれくらい?
風邪のウイルスに感染すると、平均2~5日の潜伏期間を経て、熱や鼻水などの症状があらわれます。
風邪の原因になるウイルス
風邪の原因になるウイルスとして、
ライノウイルス
コロナウイルス
アデノウイルス
RSウイルス
ヒトメタニューモウイルス
などが存在します。
ライノウイルスに感染することで発症するケースは全体の30~50%と最も多くなっており、次に多いのがコロナウイルスの10~15%です。
感染から発症するまでの期間
個人差はあるものの、ウイルスに感染してから発症するまで1〜3日程度のものが多いです。
新型コロナウイルスのように発症まで1日〜14日と幅があるものもあります。
潜伏期間は免疫力や環境の差で異なる
潜伏期間の長さは、個人の免疫力や置かれている環境でも変わると考えられます。
同じ程度の免疫力があっても、寒くて乾燥した場所にいる人の方がウイルスの繁殖が高まり、早く発症するでしょう。
赤ちゃんや子どもの場合は?
風邪のウイルスは数多く存在しているので、お母さんが感染したことのない風邪のウイルスに赤ちゃんが感染すれば、生後すぐにでも発症します。
子どもは大人よりも免疫も弱いので、風邪にかかりやすいと言えます。
赤ちゃんは生まれてしばらくは、お母さんからの免疫があるとされていますが、それはお母さんが感染したことのあるウイルスに限った話です。
生後すぐの赤ちゃんの不用意な外出は控えた方が良いでしょう。
潜伏期間中に「風邪は治せる?」
潜伏期間中にウイルスを増やさないように注意して、体の免疫が侵入したウイルスに打ち勝てば、症状が出ないで済む場合もあります。
発症しにくい「弱いウイルス」もいる
風邪のウイルスには弱いものも多く存在しています。
この場合、人の免疫が勝ち、症状が出ないまま終わりやすいです。
潜伏期間中に発症を抑えるための対策
部屋を加湿する
疲労やストレスをためない
規則正しい生活を送る
質の良い睡眠をとる
バランスの良い食事3食とる
ウイルスは湿気に弱いので、加湿しましょう。
また、部屋の湿度を上げることはすぐにできても、体の免疫を上げるのは1日では難しいです。
日頃から規則正しい生活やバランスの良い食生活を心掛け、体の健康づくりを行いましょう。
風邪のウイルスの「感染期間」はいつまで?
風邪ウイルスの感染期間は、潜伏期間と症状がなくなるまでの期間を合わせた期間で、多くは1週間程度でしょう。
ただし、個人の回復力やウイルスによって、感染期間の長さは多少前後します。
風邪の感染力はいつまで続く?
風邪の感染力が最も強いのは発症して1〜2日です。
ウイルスは、くしゃみや咳などで飛び散ります。
症状が弱くなっても咳やくしゃみ、接触などがあれば、2~3日間は他人にウイルスをうつしてしまう可能性があります。
また、寝不足や体力が落ちているのときは、症状が長引きやすくなり、感染力も維持されやすいです。
うつりやすい風邪ウイルス
ライノウイルス
コロナウイルス
潜伏期間中でも人にうつるの?
潜伏期間中でも他人へ風邪をうつすおそれはあります。
喉や鼻粘膜で繁殖しているウイルスに触れ、体内に取り入れてしまうとうつります。
潜伏期間中にうつる確率
風邪のウイルスは種類が数多くあり、差があるので一概には言えません。
しかし、免疫が低下している人・もともと免疫が低い人(子供・妊婦・高齢者・病人)は、うつる確率が上がると考えられます。
ウイルス潜伏期間中の「感染予防の対策」
風邪に感染しているおそれがあるときは、ほかの人へ感染させないように、次の対策をしてください。
こまめにうがいと手洗いをする
バランスのよい食事を心がける
睡眠を十分にとる
鼻水やたんなどを含んだティッシュはすぐに捨てる
マスクを着用する
タオルを共用しない
感染した人と同居している場合は、風邪に感染しないように、次の対策をしてください。
こまめにうがいと手洗いをする
バランスのよい食事を心がける
睡眠を十分にとる
手洗い後にアルコール消毒する
快適な室温(夏は28度、冬は20度)を保つ
湿度は50~60%程度を保つ
日中1~2時間ごとに5~10分間窓を開けて換気をする
人からうつる以外の感染経路
感染経路として
くしゃみや咳でウイルスがドアやTVリモコンなど付着
他の人がそのドアやリモコンなどを触る
そのウイルスが付いたままの手を、口や鼻に入れてしまい感染する
といったものが考えられます。
感染を防ぐ方法
風邪ひいている人はマスクをして、ウイルスが飛び散らないようにしましょう。
他者と共有することが多い、ドアやリモコンは除菌スプレー(シート)で拭いてください。
風邪を発症したときの対処法
十分な睡眠時間を確保する
食事は、油分控えめのうどんやおかゆなど消化よい食べ物を食べる
首・手首・足首を温める
常温のスポーツドリンクや経口保水液で水分補給をする
部屋の湿度は50~60%程度を保つ
しっかりと休んで、体の免疫を高めることが大切です。
また、水分を十分にとると、ウイルスを体外に排出しやすくなります。
風邪は人にうつすと治るって言うけど…ホント?
人にうつしても風邪は良くなりません。
うつされた人の潜伏期間とうつした人の症状改善のタイミングが重なることで、うつすと治るなどと言われていたようです。
できるだけ悪いウイルスを繁殖させないよう、感染したらマスクの着用をして、人に接触しないよう努めましょう。
まとめ
風邪の多くは、くしゃみや咳でウイルスが飛びだし、他の人にうつしてしまうことで拡大します。
ご自身の症状の悪化を防ぐためにも、人へうつさないためにも、内科で受診しましょう。
また、小さなお子さんや赤ちゃんから大人に感染することもあります。
近くにいる分、どうしても感染しやすいので、マスクの着用と手洗いを徹底し予防しましょう。
内科を探す
※記事中の「病院」は、クリニック、診療所などの総称として使用しています。