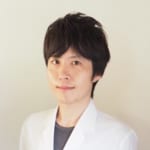「最近、体の調子を崩しがち・・・」
「休日も仕事のことばかり考えてしまう・・・」
その症状、もしかして適応障害かもしれません。適応障害の症状や対策まで、医師が詳しく解説します。
監修者
経歴
2010年名古屋大学医学部卒。2018年同大学院博士課程修了。医学博士。
名古屋大学医学部付属病院精神科などを経て、現在は複数の企業と契約し、労働者の総合的な健康状態の向上を目指して、助言や指導、研修や衛生講話を通じた安全衛生教育などといった産業保健活動に取り組んでいる。
また、総合病院心療内科にも勤務し、がん患者の終末期医療も担当している。その他、Webマガジン「現代ビジネス」で、メンタルヘルスを主なテーマに、記事の執筆・監修を行っている。
「適応障害」とは

「適応障害」は、職場の人間関係などのある特定の状況や出来事が、その人にとって、
とてもつらく耐えがたく感じられたために、心や体の調子を崩す病気です。
ストレス因子(=ストレスを引き起こす要因)を取り除く・緩和する、もしくは、ストレス因子から離れると、だんだんと調子はもとに戻ります。
「適応障害」と「うつ病」の違い

典型的なうつ病を発症している場合は、ストレス因子から離れても、気分の落ち込みが改善することはありません。
適応障害は「甘え」ではありません

ストレスに気づき、ストレスへの対処法を学ぶことは非常に重要です。
適応障害は、環境に適応することができず、心や体が疲れてしまう病気です。
決して「甘え」などではありません。
自分一人で抱え込まず、家族や親しい友人に相談することもよいでしょう。
働き方改革では、企業が労働者の健康を管理するため、産業医を巻き込むことについて触れられています。
今後、企業は労働者の健康管理ができるような組織づくりに力を入れると考えられます。
働き方改革では、労働時間の短縮に重点が置かれていますが、労働時間が減少し、時間あたりの生産性を向上させなければいけないとしたら、これまで以上に心身に負担になる可能性もあります。
職場で「適応障害になりやすい」4ケース

- 一生懸命働いているが、仕事量が多く、休めない
- 自分のペースで仕事ができない
- 仕事内容が、自分の性格や能力に合っていない
- 職場の人間関係がよくない
1. 仕事量が多く、休めない
2. 自分のペースで仕事ができない
→具体的にいうと…
- 残業時間が月に80時間以上
- 勤務時間中だけではなく、休日にも、常に仕事のことばかりを考えている
3.仕事内容が、自分の性格や能力に合っていない
→具体的にいうと…
- 自分の能力以上の仕事を任されている
- 自分の持つ知識や技術が生かされず、やりがいが感じられない
4.職場の人間関係がよくない
→具体的にいうと…
- 職場で孤立していて、困った時に相談ができない
- 同じ部署内で意見の食い違いがある
- パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントに苦しんでいる
「現場で立ち回る人」と「管理職」では、ちょっと違う
「現場で立ち回る人」で、適応障害になりやすいケース


さまざまな顧客と顔を合わせる必要がある営業の仕事は、心理的な負担が大きい職種のひとつです。
中には、クレームが多い顧客や、自分の性格とは合わない顧客と接することもあるでしょう。
プライベートであれば、そうした相手は避けることができます。
しかし、仕事となると、特に責任感が強く真面目な人は、「やらなければならない」と、無理をしてしまいます。
固定されたメンバーのみで顔を合わせて行う仕事であれば、それほどストレスを強く感じることは少ないかもしれません。
「管理職」で、適応障害になりやすいケース

これまで仕事の成績がよかったため、管理職に昇進したものの、部下の管理業務への適性がない場合に多いです。
管理職に昇進しても、なれない環境で働きにくいのであれば、適応障害を発症する場合があります。
管理職とは「マネジメント」と「意思決定の権限・責任」を担います。
したがって、仕事内容はガラっと変わることも少なくありません。
仕事を続けながら「メンタルを楽にする方法」は?

- 業務量を調整する
- 職場環境を整える
- ストレス対処法を見つける
- 自己肯定感を高める
ストレス因子にもよりますが、上記の方法が考えられます。
① 業務量を調整する

業務量を減らす方法がないか、相談してみましょう。業務プロセスの効率化の可能性も検討しましょう。
② 職場環境を整える

通勤によるストレスが原因であれば、出社する時刻を変えてみる、人間関係が原因であれば、席の配置を変えてみる、といったことを、可能な範囲で行いましょう。
業務内容に対する適性の低さが原因であれば、配置転換も検討しましょう。
③ ストレス対処法を見つける

普段から、十分な運動や睡眠、バランスの取れた食事など、ストレスに強くなるライフスタイルを心がけましょう。
また、職場でも行える、自分なりのリフレッシュ方法を見つけましょう。(業務の合間の軽い運動、昼休み中の昼寝など)
④ 自己肯定感を高める

自己肯定感とは、あるがままの自分を受け入れ、自分自身をかけがえのない存在と思える感覚のことです。
適応障害になりやすい人は、この自己肯定感が低い傾向にあると言われています。
自己肯定感を高めるためには、自分の否定的な面ではなく、良い部分に目を向けること、否定的な感情がどうしても思い浮かんでしまう場合は、「自分は過度な思い込みをしている」と認識することが重要と思われます。
自己肯定感が低い傾向にある人は、自己表現が苦手である場合が多いです。この場合、アサーショントレーニングも効果的な方法の一つです。
※アサーショントレーニング:相手の気持ちを思いやりつつ、自分の考えや気持ちを率直に表現する方法を学ぶトレーニング
病院へ行く目安

適応障害の症状には、
- 情緒的障害
- 行為の障害
の2種類があります。
①には、抑うつ気分・不安・怒り・焦りや緊張といった症状があります。
②には、暴飲暴食・過度の飲酒・攻撃的な言動があります。
職場のメンタルヘルスにおいて重要な症状の具体例として、遅刻や欠席が増える、業務の成果が上がらない、といったことがあります。
こうした症状が現れた場合は、病院を受診して治療をする必要があります。

短期間によくなる場合もありますが、6ヶ月以上も続くことがあります。
うつ病に進展してしまうこともあります。
そうなる前に、我慢せず、病院を受診することをおすすめします。
心療内科を探す
合わせて読みたい

2020-06-11
この症状は、心療内科に行くべき…?
お医者さんに心療内科に行ったほうがいい目安を聞きました。
初診で話す内容や、料金についても解説しますので、ぜひ最後まで読んでください。
心療内科を受診すべき症状目安
「これくらいで受診してもいいの?」と思ったら、その時点で受診をすることをおすすめします。
受診すべきかどうかは、「日常生活に支障をきたしている可能性があるか」を判断のポイントにしましょう。
例えば、「憂鬱で誰にも会いたくない気分で、学校や仕事に行けなくなった…」という場合は受診をしたほうがよいでしょう。
そのまま病院に行かずに病状が進むと、身体も心も動けなくなる状態になることもあり、病院への受診も考えられなくなることもあります。
受診すべき症状例
眠れない日が続いている
寝ても疲れがとれず、倦怠感がある
悩み事のせいで食欲がない、食べても美味しいと感じない
ストレスがきっかけで、2週間以上落ち込んでいる
頭にモヤがかかったように集中力が低下している
心療内科は、ストレスが原因で身体にも症状が出ている状態を治療するところです。
内科を受診しても原因が分からず症状が続いているという場合も、一度心療内科を受診してみるとよいでしょう。
心療内科を探す
「私は行ったほうがいい?」症状チェック
最近2週間で、以下の症状があるかどうかをチェックしてみましょう。
1日中、憂鬱な気分が続いている
何をしても楽しく感じない
疲れやすい、やる気が出ない
集中力や注意力が低下している
自分の価値が分からない
周りに迷惑をかけている、と感じる
将来に希望が持てない
自分の体を傷つけたり、自殺を考えたことがある
夜寝付けない、寝ても途中で起きる、寝すぎてしまう
食欲がない、または過食状態である
これらの症状が1~2個以上当てはまる場合、受診をおすすめします。
心療内科を探す
心療内科を受診するメリット
心療内科を受診すると、体や心の不調を早く楽にすることが期待できます。
早期受診することで、学校や会社を休まず、生活をしながら治療ができます。
ネットの「心療内科に行ってはいけない」という声
ネット上で、「心療内科に行ってはダメ!行ったら最後だ!」という言葉を見つけて心配です…。
ネットでは、心療内科や精神科を受診することへのネガティブなイメージも多く見受けられるため、心配になる方も多いでしょう。
しかし、症状を放置すると、さらに悪化して、日常生活も送れなくなる可能性があります。
また、薬を服用すると自己判断で薬をやめることができないため、そんなイメージを持つ方もいるかもしれません。(薬の服用を治療途中でやめてはいけないのは、他の病気でも同じです。)
心療内科の医師は、心と体の専門家です。
病院で話したことが、あなたの許可なく外に漏れることもありません。
まずは、自分がどのような状態であるのかを理解するために、受診してみましょう。
知っておきたい!初診の流れ
初めての心療内科で緊張します…。
心療内科も内科も、受診までの流れは同じです。まずは、電話やネットで初診の予約をしましょう。
予約の時点で、大まかな症状を聞かることもあります。いつ頃から、どのような症状があるのかを伝えましょう。
初診時は、以下のようなことを問診票に記入します。
いつ頃から、どんな時に症状が起こるか
今までにその症状に対して、治療を受けたことがあるか
現在、飲んでいる薬があるか
今まで大きな病気にかかったことがあるか
問診票の問いに対して、書きたくないことは無理に書く必要はありません。
医師とのコミュニケーションを通して、伝えたいことがあれば伝えるのが良いでしょう。
初診ではどんなことを話す?
一般的に、医師からは次のような質問を受けることが多いでしょう。
どんな症状が、いつから出ているのか
家族のこと
仕事のこと
生活のこと
食事をとれているか
睡眠をとれているか
希望する治療法
希望しない治療法
こちらも問診票と同様、答えたくないことは無理に答えなくても大丈夫です。
初診料はどれくらい?
保険診療の初診料は3割負担の患者の場合は約2000~4000円です。
検査の内容などで、費用は変わる場合があります。
時間はどのくらいかかるの?
初診にかかる時間は、30分から1時間程度です。
心療内科を探す
治療方法は?
心療内科での治療は、薬物療法や、精神療法を行うことが多いです。
<薬物療法>
抗うつ薬や抗不安薬、睡眠薬などの心のお薬と、お通じや腹痛などの症状に対する身体のお薬や身体全体を調整してくれる漢方薬などを使用します。
<精神療法>
精神療法では、認知行動療法を行います。認知療法とは、患者さんの物事の考え方や受け取り方に働きかけて行動をコントロールすることで、気持ちを楽にする治療方法です。
また最近では、上記の治療法以外にも、脳に対するTMS治療(経頭蓋磁気刺激法)※も、薬で効果がない人や薬の副作用が強い人に注目されています。
※外部からの磁気刺激で脳を局所的に活性化させることで、脳の血流を増加させ、低下した機能を改善する治療法
「薬がやめられなくなったら…」と不安な方に
「薬漬けになりたくない」という思いから、心療内科での治療を不安に思う人もいると思います。
薬を使って治療したとしても、症状が良くなれば、徐々に薬の量を減らすこともできます。医師の指導に従って薬の量を減らしていけば、副作用も大きくありません。
また、先述したように、治療法は薬物療法だけではありません。精神療法やTMS治療など様々な治療法がありますので、医師とよく相談して、不安のない治療法を選択するようにしましょう。
参考
厚生労働省 こころの耳:1 うつ病とは
https://kokoro.mhlw.go.jp/about-depression/ad001/
MSDマニュアル家庭版:精神障害の治療
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/10-心の健康問題/米国における精神医療の概要/精神障害の治療
沖縄県医師会:心療内科精神科の薬(2012年12月24日掲載)
http://www.okinawa.med.or.jp/old201402/healthtalk/gusui/2012/data/20121224n.html
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター:認知行動療法とは
https://www.ncnp.go.jp/cbt/guidance/about
BESLI CLINIC:問題解決療法・認知行動療法
合わせて読みたい

2022-12-27
「うつ病がなかなか治らない…」
「このまま一生治らなかったらどうしよう…」
府中こころ診療所の院長であり、YouTubeで動画配信も行っている精神科の医師、春日雄一郎先生が、うつ病や適応障害の症状が長引く理由を解説します。
うつ病や適応障害が治らず焦りを感じている方は必見です。
※動画による解説は記事末尾から
うつ病・適応障害が治りにくい4つの原因
うつ病・適応障害がなかなか治らない場合
生活習慣の乱れ
環境がよくない
考え方のクセ
躁うつ病(双極性障害)を発症している
などの原因が考えられます。
原因① 生活習慣の乱れ
昼夜逆転した生活
過度な飲酒
ほとんど家から出ない
上記に当てはまる場合は、うつ病が治りにくくなる可能性があります。
「不規則な生活リズム」「お酒の飲みすぎ」「外出せずほとんど体を動かさない」などの習慣が続くと、心身の調子が悪くなり、うつ病・適応障害の改善の遅れを招きます。
【対処法】一定の生活リズムを習慣化しよう
うつ病や適応障害を改善するためには、「どういう行動習慣を積み重ねていくか」ということが重要です。
睡眠や食事の時間を一定にする
お酒を控える
日中は外出して体を動かす
上記を習慣化して、治療にとってプラスになる行動を積み重ねていきましょう。
生活習慣を整えることで、心身の調子が整いやすくなります。
また、その行動の積み重ねが脳への刺激になり、うつ病や適応障害の改善につながると考えられます。
原因② 環境がよくない
職場に相性のよくない上司がいる
家に居場所がない
子育て・介護などでストレスを感じている
上記のように、職場や家庭の環境がよくない人は、うつ病や適応障害が治りにくくなることがあります。
うつ病・適応障害の症状は、日々の行動だけでなく、環境からも大きな影響を受けます。ストレスの多い環境で過ごす時間が積み重なると、症状の改善が遅れる原因となります。
【対処法】「転職・異動」「支援サービスの利用」を検討しよう
環境がよくないと感じる場合、
転職・異動の相談をする
家族と話し合いをする
自治体のサポート窓口を利用する
といった方法で、環境を変えることが選択肢の一つとなります。
環境の変化には良い面も悪い面もあるため、一概に「環境を変えるべき」というわけではありません。
ただし、「どうしても今の環境と相性が悪い」と感じる場合は、選択肢の一つとして考えてみるといいでしょう。
職場の環境が合わないと感じる場合は、「転職を検討する」「上司や人事部に異動の相談をする」などの方法もあります。
家庭内でストレスを感じている場合は、まずは家族と話し合うことが必要なケースもあります。
子育てや介護などでお悩みの場合は、自治体のサポート窓口を活用してみるのもいいでしょう。
子育てや介護に関するお悩みは、お住まいの自治体の子育て支援センターや、地域包括支援センター※などの機関で相談可能です。
※地域包括支援センターとは
主に自治体が設置する高齢者の健康や生活をサポートする施設。
▼参考
地域包括ケアシステム(厚生労働省)
原因③ 考え方や性格のクセ(完璧主義・人と比べる)
自分を責めてしまう
完璧主義
他人と自分を比べる
上記のような考え方・性格のクセがある人は、うつ病や適応障害の治療が遅れる可能性があります。
「考える」ということも一種の行動です。自責や他人との比較など、自分にダメージを与える思考を繰り返すことも、病気の改善を妨げる行動を積み重ねる行動になります。
【対処法】「前向きになれる考え方」を練習しよう
自分にダメージを与える考え方のクセがある人は、「自分も他人も責めない」「前向きになれることを考える」といったことを意識するといいでしょう。
ただし、考え方が根強いクセになっている場合、すぐには変えにくいこともありますよね。
その場合は、
出てきた考えを真に受けすぎず、なるべく受け流す
否定のクセを薄めて、成功体験を徐々に積み重ねる
この2つを心がけてみてください。これらの思考を積み重ねていくことが、結果として、否定的な考えが出てくる頻度を減らすことに繋がります。
原因④ 躁うつ病(双極性障害)を発症している
抗うつ薬などによる治療を続けていて、生活習慣・環境・考え方などの見直しを行っているにもかかわらず、症状の改善が見られない場合は、躁うつ病(双極性障害)を発症している可能性があります。
躁うつ病ってどんな状態?
躁うつ病とは、気分が高揚して活動的になる「躁状態」と、気分が沈んで意欲がなくなる「うつ状態」を交互に繰り返す状態です。
人によっては、躁状態の症状が軽くて期間が短く、うつ状態が長く続く「双極性障害Ⅱ型」のケースもあり、この場合は一般的なうつ病との区別がつきにくいです。
うつ病と躁うつ病は使う薬が違うので、この見極めができていないと、病気が長引く恐れがあります。
躁うつ病かを判断する4つのヒント
過去を振り返って、躁気味な時期があった
家族に躁うつ病の人がいる
周期的にうつ病を繰り返している
抗うつ薬を使うと躁状態になる傾向がある
躁うつ病かどうかを判断するヒントとして、上記の4つが挙げられます。
「ある時期だけ妙に活動的だった」「ある時期だけ妙にお金を使っていた」など、過去に躁気味な期間があった場合は、躁うつ病である可能性が出てきます。
自分ではわからなくても、『ちょっといつもと違う』『いつもより妙に元気だね』などと、周りの人から言われる時期があったかどうか、ということも参考になります。
また、家族に躁うつ病の人がいると、発症の可能性が少し高くなると言われています。
その他、周期的にうつ病の症状を繰り返す場合や、抗うつ薬を使ったときに躁状態になる傾向がある場合も、躁うつ病を発症している恐れがあると考えられます。
躁うつ病を疑う場合は主治医に相談を
躁うつ病の発症を疑う場合は、早めに主治医に相談しましょう。
うつ病と躁うつ病では、治療に使う薬が違います。そのため、うつ病か躁うつ病かを的確に判断することは、症状を早く改善するために、非常に重要であると考えられています。
▼動画による解説はこちら
※本記事は、チャンネル運営者の許可を得て作成しています。
≪チャンネル紹介≫
こころ診療所チャンネル【精神科医が心療内科・精神科を解説】
府中こころ診療所の院長であり、YouTubeで動画配信も行っている精神科の医師、春日雄一郎先生が、うつ病・適応障害・パニック障害など、こころの不調やその対策について、わかりやすく解説。
こころの不調を抱える方が、少しでも症状を改善するヒントとなるような情報の提供を目指しています。
▼参考文献
『パニック障害』と『適応障害』(武田病院)